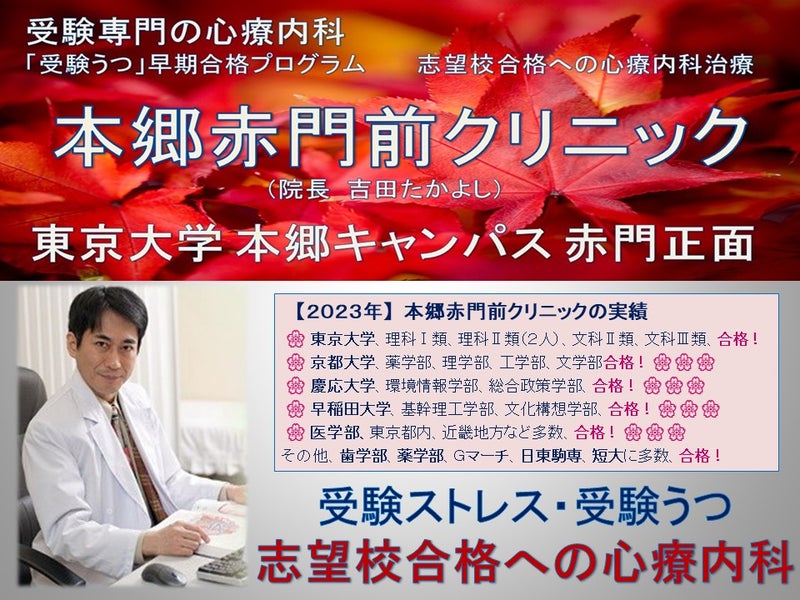勉強の集中力を最大にする休憩のとり方とは?

受験生が志望校への合格を勝ち取るのに、受験勉強に関して最も大切なのは集中力です。
そんな勉強の集中力は、休憩の取り方と密接に結びついており、入試で合格を勝ち取るには、集中力が最も高まる最も効率の良い休憩のとり方を実践していただきたいです。
では、勉強の合間の休憩は、どのように取るのがベストなのでしょうか?
実は、脳医学の研究でその答えを導き出す研究が次々と発表されているんです。
これを知っておくと、トータルの勉強時間が同じでも、よりたくさんの知識を脳に蓄積できます。
受験では圧倒的に有利になりますので、受験生を専門に診療している心療内科医の経験と専門知識をもとに、わかりやすく解説します。
また、ご家庭で簡単に実践できる「勉強の集中力を高める方法ベスト10」もありますので、そちらもご紹介したいと思います。

あなたの勉強は休憩の取り方で損をしている!
私は、脳医学に基づく効率的な勉強法について講演会を開催していただく機会が多いのですが、そんなとき、勉強の合間の休憩の取り方について、受講生の方からご質問をよくいただきます。
脳科学の観点から言うと、ほとんどの受験生が適切な休憩の取り方ができておらず、逆に言えば、改善の余地はとても大きいのです。
ただし、それ以前の問題として、休憩の回数が少なすぎる受験生がとても多いのです。
これによって勉強の効率が悪くなり、受験に関して損をしてしまっています。
長くダラダラ休まず、短く効率よく休む回数を増やす!
誤解してほしくないのですが、受験生は休憩をいっぱいとって、楽をしていいという意味ではありません。
多くの受験生が、休憩のとり方が無計画なため、スマホをダラダラと見るなど、とっても効率の悪い休憩方法で、時間を浪費しています。
しかも、長時間、スマホを見続けると、脳を無駄に使ってしまうため、脳の機能を回復させるという点では、脳医学的にちっとも休憩になっていないケースが多いのです。
休憩時間についても、ストップウォッチなどできっちり時間を測定し、脳を効率よくしっかり休ませるということが大前提です
休憩による集中力の回復効果の特徴とは?
その前提のうえで、実験結果の分析データを見ると、適切な休憩を取る効果は絶大です。
休憩の後には集中力が上がり、勉強の効率は大幅に上昇するのです。
もちろん、休憩を取るぶんだけ、勉強時間は減ります。
しかし、脳に適切な形で休憩を取れば、勉強時間が減るマイナスの効果より、集中力が高まることで勉強の密度が上がるプラスの効果がはるかに上回るのです。
とはいっても、あまりにも勉強時間が減りすぎると、集中力が上がっても、勉強時間が減った分を取り返せません。
では、どれくらいのタイミングで休憩を取るのがベストなのか気になりますよね。
これについても実験データがあり、小論文など創造的な脳機能を使う勉強については、より長い時間、まとまって行うほうが勉強の効率は高まるという結果が出ています。
一方、計算や記憶など、単純な脳機能を使う勉強については、より短い時間を勉強するごとに、小刻みに休憩を取るほうが、勉強の効率が高まる傾向がデータとして出ています。
脳のどの部分のどういう能力を使うかで、理想の勉強時間は変わってくるというわけです。
休憩の効果が最大化する実験データとは?
平均を取ると、大学受験の一般入試に対する典型的な勉強の場合、30分勉強で、5分休憩が最も集中力が高まるという実験データが出ています。
意外に短い時間だと感じた方が多いと思いますが、これはあくまでも集中力に限定したデータで、杓子定規に30分を厳密にキープする必要はありません。
ただし、本当の意味のトップ水準の集中力は、一般的な常識よりはるかに短い時間しか維持できなということだけは、頭に入れておいていただければと思います。
それを考慮に入れた上で、実際には、これからどんな勉強をするのかその中身に応じて、休みを取るまでの勉強時間の長さを柔軟に調節するのが良いと思います。
また、これも実験データを見るとよくわかるのですが、休憩の効果は、5分まではすごく大きく、その後は、グッと小さくなります。
だから、1時間、勉強して10分休憩するより、30分勉強するごとに5分、休憩したほうが、勉強の成果は上がるということです。
ただし、実際には50分ぐらいまとめて勉強した方が都合が良いような受験勉強が多くありますので、そこは柔軟に対応しましょう。
ただし、1時間を超えて連続して勉強するのは、よほど勉強の中身にメリットがない限り、やめたほうが、受験勉強の効率の点で有利だと言えます。
休憩の取り方が悪いとスマホ依存の原因に!
実際、ほとんどの受験生は、連続して勉強する時間が長すぎています。
それで脳が疲弊して、いったん休憩を取ると、スマホを眺めながら、延々と時間を浪費しているんです。
大事な脳の機能を低下させ、おまけに貴重な時間まで捨てる事になっている・・・。
実際、休憩の取り方が悪いことが、スマホ依存の原因になっている場合もあります。
それよりも、1回あたりの勉強は、より短い時間に限定して集中し、間に短い時間の休憩時間をはさんで、さらに休憩も集中して休憩することで脳をより効率よく回復させることをお勧めします。
そうなっていない受験生は、勉強習慣を今すぐ、改めてほしいですね。
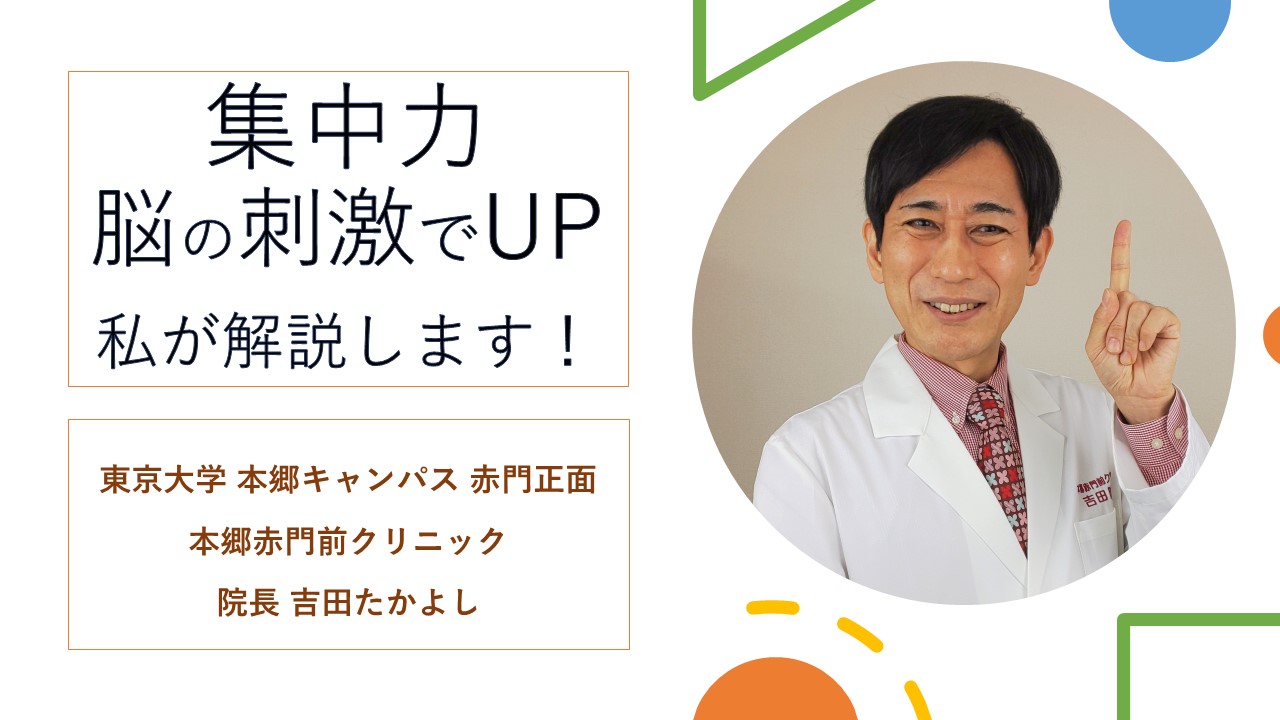


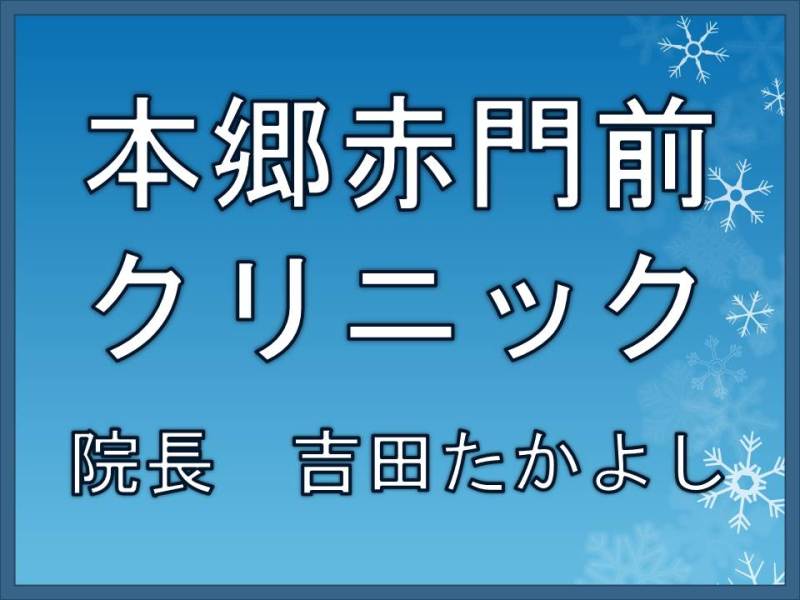
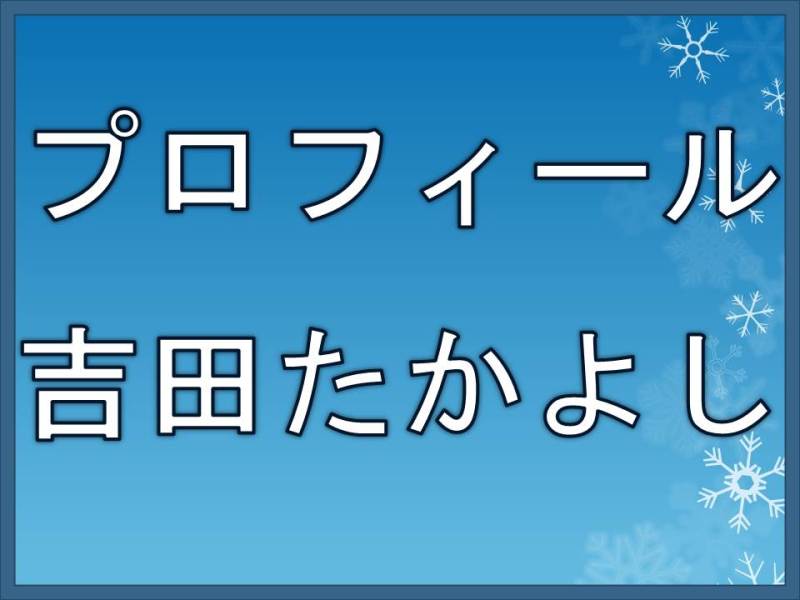




 <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br>