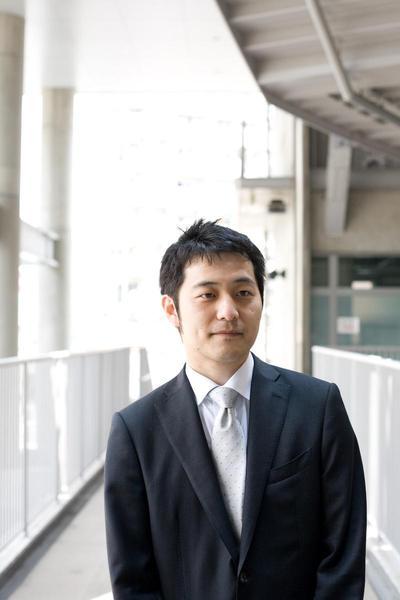若者と社会をつなぐ支援NPO/ 育て上げネット理事長工藤啓のBlog
若者支援、NPO経営、ファンドレイズ、CSR、ソーシャルビジネスなど、日々の生活や仕事で気がついたことを書いていこうかと思います。
プロフィール
カレンダー
月別
ブログ内検索
お気に入りブログ
2014年06月13日(金)
無業社会 -働くことができない若者たちの未来-を上梓しました。
テーマ:ブログ無業社会 働くことができない若者たちの未来 (朝日新書)/朝日新聞出版

¥821
Amazon.co.jp
本日、立命館大学の西田亮介先生との共著を上梓しました!
ぜひ、お手にとっていただけたら嬉しいです。
西田さんにも本書紹介にあたり寄稿いただき、下記に添付しました。
以下、育て上げネットメルマガ抜粋。
---
「無業社会 -働くことができない若者たちの未来-」
W杯開幕と同日、朝日新書より「無業社会 -働くことができない若者たちの未来-」を上梓いたしました。
http://amzn.to/1kK45E8
若年無業者に関する詳細なデータが乏しいことに問題意識を持ち、まずは育て上げネットの手持ちデータを分析、解析して社会に発信することを決めました。
立命館大学の西田亮介先生に共同分析をお願いすることで中立性を担保しようとしましたが、いくつかの研究助成は採用されませんでした。そこで近年注目されているクラウドファンディングを活用し、当初予定していた資金は8時間で達成、その後も協力者は増え続けました。
READYFOR?:https://readyfor.jp/projects/underserved-youth
その後、出版した「若年無業者白書 -その実態と社会経済構造分析-」のフルカラー版は早々に完売し、現在はKindle版のみとなっています。
http://amzn.to/1g6nUSQ
また、一昨日、この白書は韓国版となり、現地にて発表されました。現在は無償でダウンロードができる期間となっています。現在は英語版の発行に向けてファンドレイジングの途中です。
http://www.hamkke.org/news/notice_view.asp?Idx=2255
しかしながら、白書はデータ集であり、数値と解釈のみとなっており、一般的に広まるのは難しいのではないかという課題意識を持っておりました。
そんななかで、朝日新聞出版さまより声をかけていただき、白書共著者の西田先生と新書執筆をさせていただけることになりました。
-------------------------------------------------------------
『 無業社会 -働くことができない若者たちの未来- 』(朝日新書)
著 者:西田亮介 / 工藤啓
出版社:朝日新聞出版
価 格:\821
(抜粋)本書では、誰もが無業になりうる可能性があるにもかかわらず
無業状態から抜け出しにくい社会を「無業社会」と呼んでいる。
【はじめに】
【第一章】 なぜ、いま「若年無業者」について考えるべきなのか
【第二章】 「働くことができない若者たち」の履歴書
【第三章】 「働くことができない若者たち」への誤解
【第四章】 「無業社会」は、なぜ生まれたか?
【第五章】 「無業社会」の日本の未来
【第六章】 若年無業者を支援する社会システムのあり方
【第七章】 「誰もが無業になりうる社会」でNPOが果たす役割
【おわりに】
amazon:http://amzn.to/1kK45E8
-------------------------------------------------------------
育て上げネットの職員の力を借りて、ケースを紹介しながら、政府統計に留まらない、独自調査である「若年無業者白書」からのデータを引用、解説しました。
西田先生からも下記コメントをいただいていますが、「現場発信」の書籍では埋めることが難しい部分を丁寧にフォローしていただきました。
「新書」×「共著」というスタイルは初めての経験でしたが、時間をかけて西田先生とコミュニケーションを取りながら執筆いたしました。
みなさまにお読みいただけましたら、大変嬉しいです。
育て上げネット
工藤 啓
---
【寄稿】
「『無業社会』を回避し『若年無業者』についてのコミュニケーションを促すために」
西田亮介(立命館大学大学院先端総合学術研究科特別招聘准教授)
なぜ、いま、改めて「若年無業者」についての、新書を書くことになったのだろうか。しかも、「無業社会」という、ともすれば大風呂敷と、ややミスリーディングな気配がする題目を冠して。
すでに「ニート」についての(ときに誤った)言説は、世間に少なくないから、「やれやれ、またこの手の類書か」とお思いになった方もいらっしゃるのではないか。とりわけ、このメルマガをお読みのみなさんは、当事者や家族、支援者といった、「思い入れの深い」方々が中心と思われるので、尚更、そのような方がいらっしゃっても不思議ではない。
先日、朝日新聞出版の広報誌『一冊の本』に、「なぜ、いま改めて若年無業者の問題を考えられるべきなのか」という主題で原稿を寄せた。この小文はある意味では、表裏一体となっている。
前者は「若年無業者の問題と直接的な利害関係に乏しい人が、なぜ本書を今読むべきか」を論じていて、後者は「若年無業者の問題と直接的な利害関係にある人も、なぜ(類書も少なくない)本書を手に取るべきか」を説明している。
なお、前者についても、育て上げネットのWebにもリンクが張られているので、以下のURLを参考にしてほしい。
http://www.sodateage.net/news/1101/
当事者や家族、支援者の方々にとっては、若年無業者についての問題の重要性は自明かもしれないが、世間一般ではそうとは限らない。すでに重要視されており、対策への合意があれば、この分野は、現在のようないささか混乱した状態にはなかったはずだ。
社会においては、数多の「社会問題」がせめぎ合っている。多くの直接利害関係のない人にとっては、そのいずれもが、それなりに重要で、同時に、それなりに重要ではない。
では、どのように、無関係な人たちを巻き込んでいくのか。彼らの耳目を引き、共感を獲得していくのだろうか。
ひとつは、まず無関係と思えた問題を、自分たちにも関係する問題だとして提示することである。もうひとつは、合理性や生産性の観点である。結局、ひとは経済的な誘因に、極めて敏感に反応する。むろん「善意や良心など存在しない」などということを言っているわけではなくて、善意や良心は存在するだろうが、それらがいつ機能するのか、どの程度機能するかを正確に予測することは極めて困難である。
良心や善意と比較して、経済的評価は計測しやすいし、説明しやすいというだけである。だったら、こちら「も」利用しない手はない。
本書は、刺激的な題目のもと、事例と2000人を上回る当事者のデータに基づいた定量的な分析をとりまとめ、さらに日本の社会システムの発展の概略を振り返りながら、多角的に若年無業者の問題を読み解いている。
肯定的な視点から入っても、否定的な視点から入っても、最終的にはこの問題の適切な解決こそが、日本社会にとって、有益である、という結論に至っている。
その意味において、本書は日本社会のあらゆるステイクホルダーが「無業社会」を回避し、抜け出し、「若年無業者」についてのコミュニケーションを促すことを目的に執筆されたということができる。
むろん、このような冷め切った見方は共著者の工藤さんの合意を得たものではなく、西田の私見に過ぎないが、当事者、家族、支援者のみなさんとは異なった視点で、若年無業者の問題を見ると、どのように見えうるのか、というひとつの思考実験として、ぜひとも本書を手にとっていただければと思う。
西田亮介